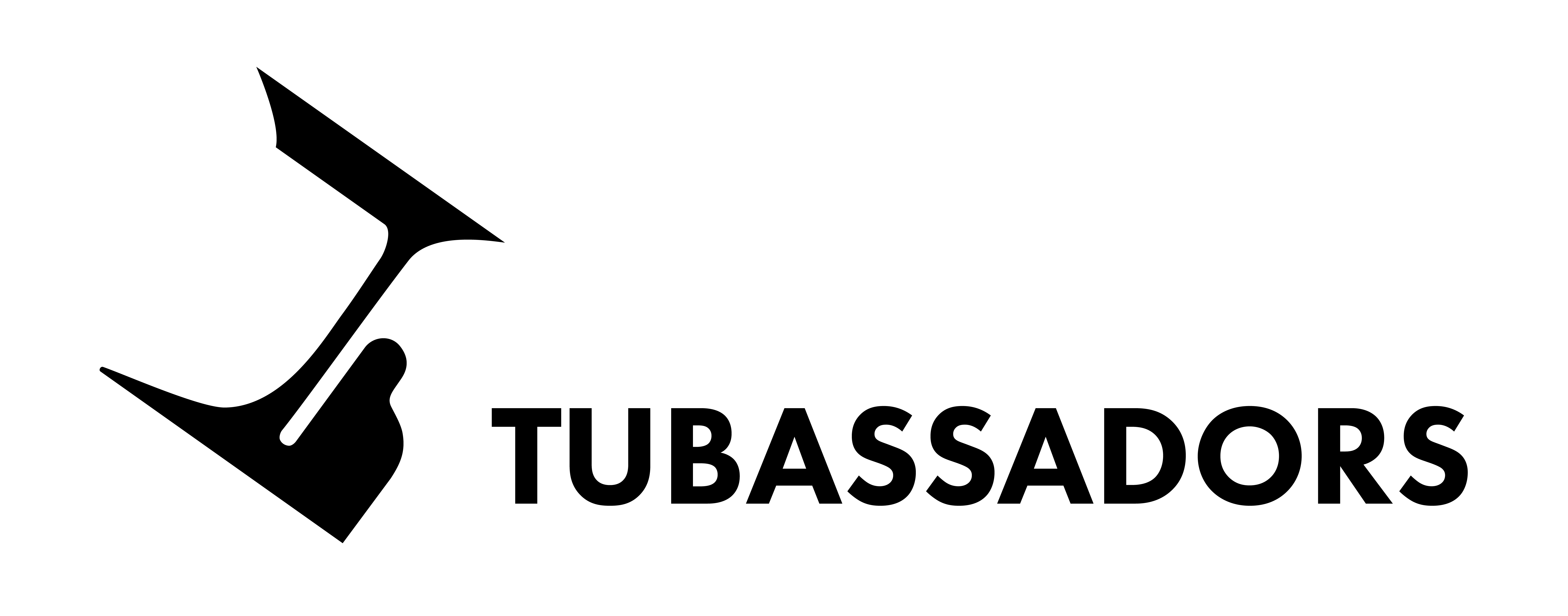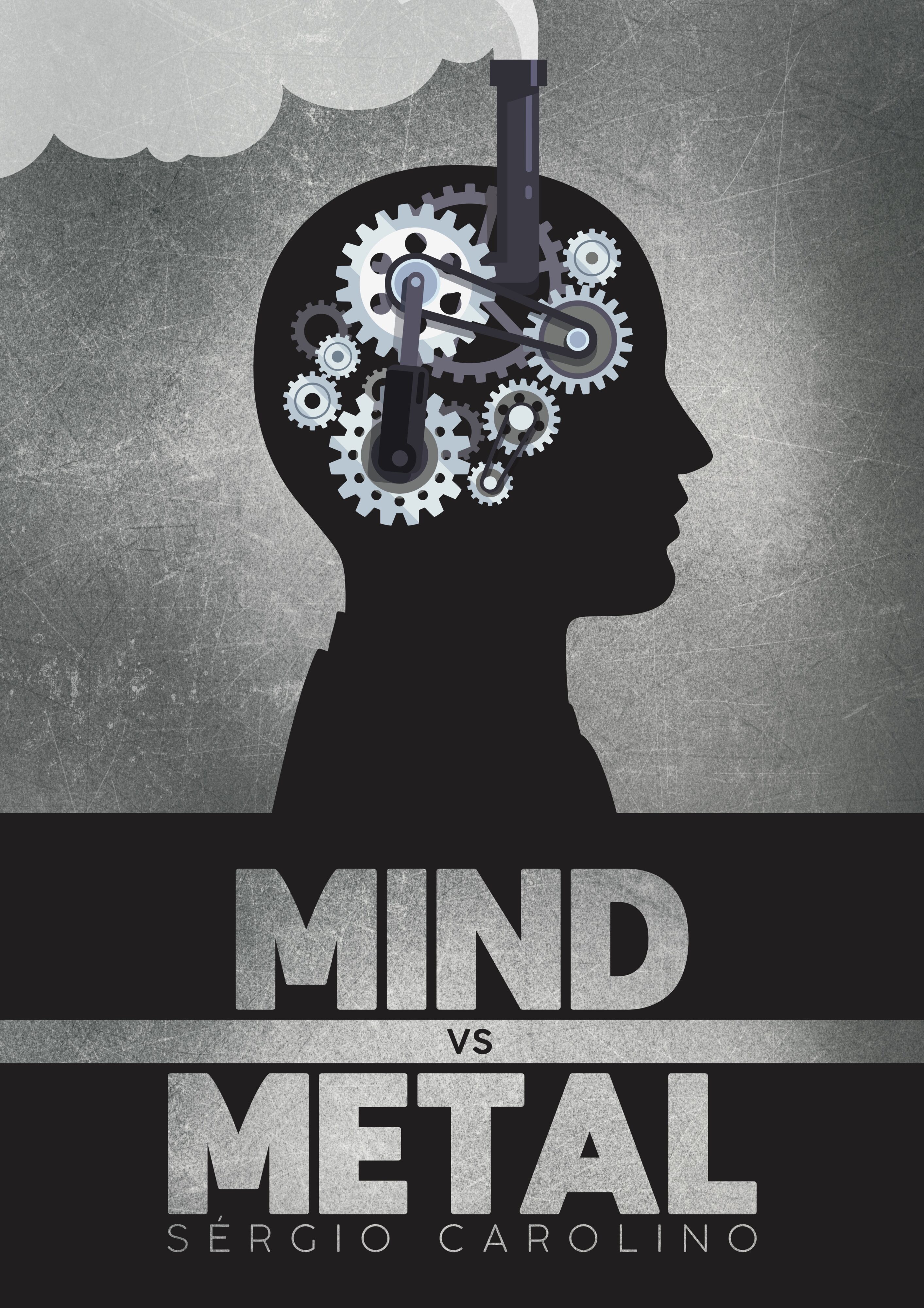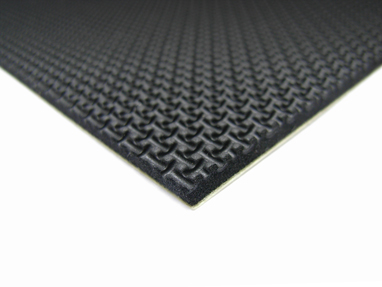Mind vs Metal
どうもこんにちは、西部です。世界的なチューバ奏者であり、私の師匠でもあるセルジオ・カロリーノ氏から学んだ最も大きなことは、彼の演奏に対する考え方の部分です。もちろん、あの特別な音から影響を受けている部分も多いのですが、やはり根本的にどんな考えで、チューバと向き合っているのかという部分はもっと多くの人に知ってほしいと思っています。
セルジオはMind vs Metalという本を書いており、そこに彼の考え方がまとまっているので、英語版しかありませんが、気になった方は是非原文を読んでみることをおすすめします。出版社から直接購入できます→こちら
独特な言い回しも多いので、今回は日本で唯一のセルジオの弟子の私が直接彼に習った知識を活かして、Mind vs MetalとFlowについて、大きく2つのトピックについてまとめます。
この本を実際に読んでいただけると、今回のブログの内容ももっと深いものになると思います。
セルジオ・カロリーノの「Mind vs Metal」とは?
セルジオが様々なところで発信している、「Mind vs Metal」という考え方ですが、文章を読んだだけでは正直全て理解するのは難しいように思います。
彼の考えを総合してまとめると
セルジオが語る 「Mind vs Metal(心 vs 金属)」 とは、演奏における「精神的な要素」と「物理的な要素」の対立と調和 を意味しています。
彼は、金管楽器の演奏が単なる技術的な作業ではなく、「心」と「身体」のバランスを取ることによって最大限の表現が可能になる という考えを持っています。

1. 「Mind(心)」= 精神的な要素と音楽的な表現
「Mind(心)」とは、演奏者の精神的な状態や、音楽的なイメージ、感情の表現 を意味します。セルジオは、金管楽器の演奏において 「音楽的な意図」や「表現の自由」 を常に頭に持っておくことが大事だと話していて、A.ジェイコブスのSong & Windの考え方に近いです。まず歌がある、まず音楽があって楽器はそれを表現するツールに過ぎないということです。
例えば…
- 音楽のイメージを持つこと(どんな音を出したいのか?)
- 音楽の流れ(フロー)を意識すること (後述のフローとは別の意味)
- 演奏への没入と集中(心をオープンにし、演奏に身を委ねる)
- リラックスして演奏すること(緊張しすぎず、自然に音を出す)
- 音楽的なストーリーを考えること(ただ音を出すのではなく、メッセージを伝える)
まとめると、「良い演奏とは、単に技術的に正しい音を出すことではなく、聴衆を感動させること」 であり、そのためには、「精神的なコントロールと音楽的なビジョンが不可欠」であるということです。
2. 「Metal(金属)」= 物理的な演奏技術
セルジオが言っている「Metal(金属)」とは、楽器そのものや演奏技術、演奏者の体のことを指しています。
例えば…
- 全調のスケールを正確に5オクターブ自由自在に演奏できる技術
- 全てのアーティキュレーション(スタッカート・アクセントetc.)
- あらゆるテンポとスピードで演奏できる技術
- サウンドの色や質感の引き出しの多さ
- 音程・ダイナミクスレンジ・アーティキュレーション
- ジャズやロックなど様々なジャンルへの対応力
- 筋肉や持久力(口の筋肉、体の使い方など)
金管楽器の演奏は、楽器を正しくコントロールする技術が欠かせません。楽器の仕組みを理解し、適切な練習を積み重ねていかなければ習得できません。でも、セルジオはこうした「金属的な要素」だけでは、本当の音楽は生まれないと僕も何度もレッスンで言われました。
「楽器は金属でできていて硬いんだから、これに勝とうとしてもダメだよ」当時うまくコントロールできないチューバを無理やり吹こうとしていたときにセルジオに言われた言葉です。
3. 「Mind vs Metal」= 両者のバランスを取ることが鍵
セルジオは、「Mind」と「Metal」は対立する概念ではなく、両者のバランスを取ることが重要 だと本の中で書いています。本人の言葉を借りると、
「この戦い(Mind vs Metal)は、決して勝つことのできない戦争である。しかし、それを理解し、毎日工夫しながら乗り越えていくことが、最高の音楽を生み出す鍵となる。」
つまり、技術(Metal)を磨くだけでは不十分であり、心(Mind)の持ちようを意識しなければ、本当に良い音楽を生み出すことはできないということです。
逆に、精神的に良い状態を作ることができても、基本的な技術が欠けていれば、思い通りの音を出すことはできません。まぁ当たり前といえばそうなのですが、これが実際むずかしいバランスなんですよね。
演奏においては 「心と身体が一体となる瞬間」 を追求するべきというのが彼のコンセプトです。
4. 実践への応用:「Mind vs Metal」をどのように意識すべきか?
概念的な話でピンとこない方もいると思いますので、実践的に取り入れるならどういうことに気をつけるか書いてみます。
「Mind(心)」= 音楽的なアプローチを強化する
- 楽譜を読むだけでなく、曲のストーリーや情景・感情・温度…ect.を考える
- 理想の音を頭の中で思い描く
- 本番前のルーティンを作り、自分が演奏に没頭できる精神状態をつくる
「Metal(金属)」= 基本的な技術を磨く
- 全スケール・アルペジオ・全音域・全音量での練習を徹底する
- リラックスしたフォームを維持する
- テンポやリズムを正確に練習する
「Mind vs Metal」= 両者のバランスを取る
- 練習の際、「これは技術的な練習か、それとも音楽的な練習か?」と考える
- 技術的な課題に集中する時間と、自由に音楽を表現する時間を使い分ける
- 緊張しているときは「Metal」に頼りすぎていないか?楽譜に縛られすぎていないか?と自問する
- 日々の練習を通じて、必要な技術や感覚を「無意識レベル」で使えるようにする。
5. 技術だけでも、感情だけでもダメ。両方が揃ってこそ本当の音楽になる
セルジオの「Mind vs Metal」は、単なる演奏技術の話ではなく、音楽を通じて自己を探求する哲学的な概念 でもあります。
レッスンでも、この部分をちゃんと理解していないと、「お前は根本的に私の考えを理解できていない」と怒られてしまいます笑
技術だけの演奏では人を感動させることはできないし、演奏で点数を取るためだったり、人にテクニックを見せびらかすような演奏はセルジオの考え方とは遠い存在にあります。
技術的な努力と精神的な成長の両方を意識することで、より深い音楽表現が可能になる、そしてそれが聴衆を真の意味で感動させることができるわけですね。
彼の言葉を改めて引用すると、
「私たちは学び続ける存在であり、心と身体のバランスを取りながら音楽を作り上げていく。」
「あなたは、超絶技巧のヴィルトゥオーゾである必要も、スターである必要もありません。ただ、あなた自身であれば良いのです!」
このMind vs Metalという考え方のベースとなっているのが、次に説明するフロー理論です。
FLOW. Relax, and let it FLOW
「自分の音楽に完全に没頭し、心の底から楽しむことで、最高の演奏が生まれる。
セルジオがもう一つ大事にしている考え方として、フロー状態という概念です。
息をもっと流して吹いて!というアドバイスでフローと使うことも多々ありましたが、演奏に対する考え方としてはフロー理論の方を指しています。
ちゃんと本人から聞きましたので間違いないです笑

1. フローの特徴
まずはフロー理論とはどういうことかおさらいします。
チクセントミハイは、フロー状態に入るための条件として、以下の要素を挙げています。
- 明確な目標がある – 何を達成すべきかがはっきりしている。
- 即時のフィードバック – 行動の結果がすぐに分かる。
- 挑戦とスキルのバランスが取れている – 難しすぎず、簡単すぎない課題がある。
- 集中力が高まる – 注意が完全に活動に向けられる。
- 自己意識の消失 – 周囲の評価や自分の意識が薄れる。
- 時間の感覚が変わる – 「時間があっという間に過ぎる」と感じる。
- 活動そのものが目的になる – 報酬ではなく、活動自体が楽しい。
2. フロー状態に入る方法
フローに入るためには、挑戦レベル と スキルレベル のバランスを取ることが重要です。
チクセントミハイは、挑戦が大きすぎると不安を感じ、逆に簡単すぎると退屈してしまうため、「ちょうどよい難易度」の活動を見つけることが鍵だとしています。
- 挑戦が高く、スキルも高い → フロー状態
- 挑戦が高く、スキルが低い → 不安
- 挑戦が低く、スキルが高い → 退屈
- 挑戦が低く、スキルも低い → 無関心
セルジオ・カロリーノとチクセントミハイのフロー理論の共通点
セルジオの「フロー」の概念は、心理学者 ミハイ・チクセントミハイ が提唱した フロー理論 から影響を受けています。
チューバの演奏においてこれがどう関係してくるのかまとめていきます。フロー理論の特徴ごとにセルジオの考えを整理してみます。
1. 没入することの重要性
フロー状態に入ると「時間の感覚がなくなり、完全に目の前の活動に没頭する」とされています。
演奏において完全に没入することが大切です。セルジオの言葉を引用すると、
「音楽とは、歌うことに他ならない!」
「演奏の流れに身を任せることで、最高の表現が生まれる。」
演奏に集中し、心と身体を一体化させることで、自然と音楽が流れ出す。
この考えは、チクセントミハイの「最適な経験(optimal experience)」の概念と同じですね。
緊張していたり、音を外さないように…とかって邪念があると、フロー状態になれないんですよね。
2. 挑戦とスキルのバランス
「挑戦のレベル」と「スキルのレベル」のバランスが大事である。
- 挑戦が難しすぎると不安を感じる
- 簡単すぎると退屈してしまう
- ちょうどよい挑戦があると、フロー状態に入れる
演奏の難易度とスキルのバランスを適切に保つことが、音楽の楽しさを最大限に引き出すポイントだと言っています。
彼の言葉を借りると
「演奏の課題を適切に設定し、成長を楽しむことが重要だ。」
「音楽を自由に表現できるレベルを目指し、挑戦を続ける。」
「成功も失敗も、あなたの心の持ちよう次第である。」
やたらと難しい曲を吹くだけで必死になって取り組んでも、良い演奏にはならない。音符だけ完璧に並んだとしてもそれはフロー状態ではなくて、音楽的には内容が薄いものになります。
それでも、自分ができる限界ギリギリに挑戦することが大事なので、簡単すぎる音楽ばかりでは上達しないということです。
ゲームでも「敵が弱すぎる」と飽きるし、「敵が強すぎる」と負け続けてやる気なくなりますよね?
楽器の練習も同じで、「頑張ればクリアできそう!」なレベルを選ぶと、フローに入りやすくなります。
これを最適な状態に保つのが難しいからこそ、プロのレッスンを受けることが大事なんです
3. 内的な動機が鍵となる
フロー状態に入るためには「活動そのものが楽しい」と感じることが不可欠だとされています。
これは 「内発的動機づけ」 と呼ばれていて、報酬のためではなく、純粋に活動を楽しむことが重要という考え方です。
音楽を「仕事」として捉えるのではなく、「純粋に楽しむもの」として考えることが、良い演奏につながるとセルジオはよく語っていて、あれだけ多くのCDやプロジェクトも彼のオーケストラの給料から出資したりしているんですよ。
自分が純粋に良いと思ったプロジェクトをやることが大事というのは、チューバサダーズのような活動をメインの軸にしている理由にもなります。チューバ四重奏、めっちゃ楽しいですからね。
「演奏を楽しむことが、聴衆を惹きつける音楽を生む。」
「ただの練習ではなく、音楽そのものを楽しめる時間にする。」

4. 自己意識の消失と演奏の自由
フロー状態では「自己意識が消え、活動そのものに没入する」 とされています。
難しい表現ですが、簡単に言うと演奏中に余計なこと考えるなってことです。
うまく演奏しないと、ハイトーン外したらカッコ悪いなぁ、〇〇さん見に来てるなぁ、ここは盛り上がるところがから大げさにやってみようとかですね
音楽を「音楽っぽく」聴かせるための小細工みたいなものはやめましょうということです
「音楽は自由であるべきだ。意識しすぎると、流れが止まってしまう。」
「演奏中に『うまくやらなければ』と考えるのではなく、音楽に身をゆだねること。」
これがチクセントミハイの「自己の喪失(loss of self-consciousness)」と近い考え方です。
5. フローと演奏の関係
演奏技術の向上についてだけでなく、心の状態が音楽・演奏に影響を与えます。
もうこれは説明するまでもなく、皆さん経験したことありますよね。
「緊張や不安があると、音楽の流れが止まってしまう。心を落ち着け、音楽に没入することで、最高のパフォーマンスが生まれる。」
「忘れないでください:金管楽器の演奏技術は、身体のコントロールだけでなく、心のコントロールも同じくらい重要なのです。」
この心を落ち着けて、音楽に没頭する言う部分が、フロー理論における「高いパフォーマンスはフロー状態から生まれる」という考えと同じですね。
没頭することがいかに難しいか…。永遠の課題ですね
実際に、スポーツ選手やアーティストが最高のパフォーマンスを発揮する際には、完全に没入した状態=フローに入っていることが多いらしいですよ。
わかりやすく表にまとめてみます
| フロー状態に入る条件 | チクセントミハイ | セルジオ・カロリーノ |
|---|---|---|
| 没入と集中 | 時間の感覚が消え、完全に集中できる | 音楽とは、歌うことに他ならない! |
| 挑戦とスキルのバランス | 適度な挑戦がフローを生む | 演奏の課題を適切に設定し、成長を楽しむことが重要だ |
| 内的動機の重要性 | 報酬ではなく、活動そのものを楽しむ | 音楽を「仕事」として捉えるのではなく、「純粋に楽しむもの」として考えること |
| 自己意識の消失 | 自分を意識せず、活動に没頭する | 演奏中に『うまくやらなければ』と考えるのではなく、音楽に身をゆだねること。 |
フロー状態に入ることで、音楽家として最高のパフォーマンスが引き出されると言うことですね
まとめ
「Mind vs Metal」とは演奏におけるメンタル的な要素(Mind)とテクニカルな要素(Metal)のバランスを取ることの重要性を示した考え方で、フロー状態とはスポーツで例えるとゾーンに入った超集中状態のようなもの。
基礎練習やその他の練習もこの考え方がベースとなっているので、次の記事では実際に練習にはどう取り入れるのかについてまとめていきます。