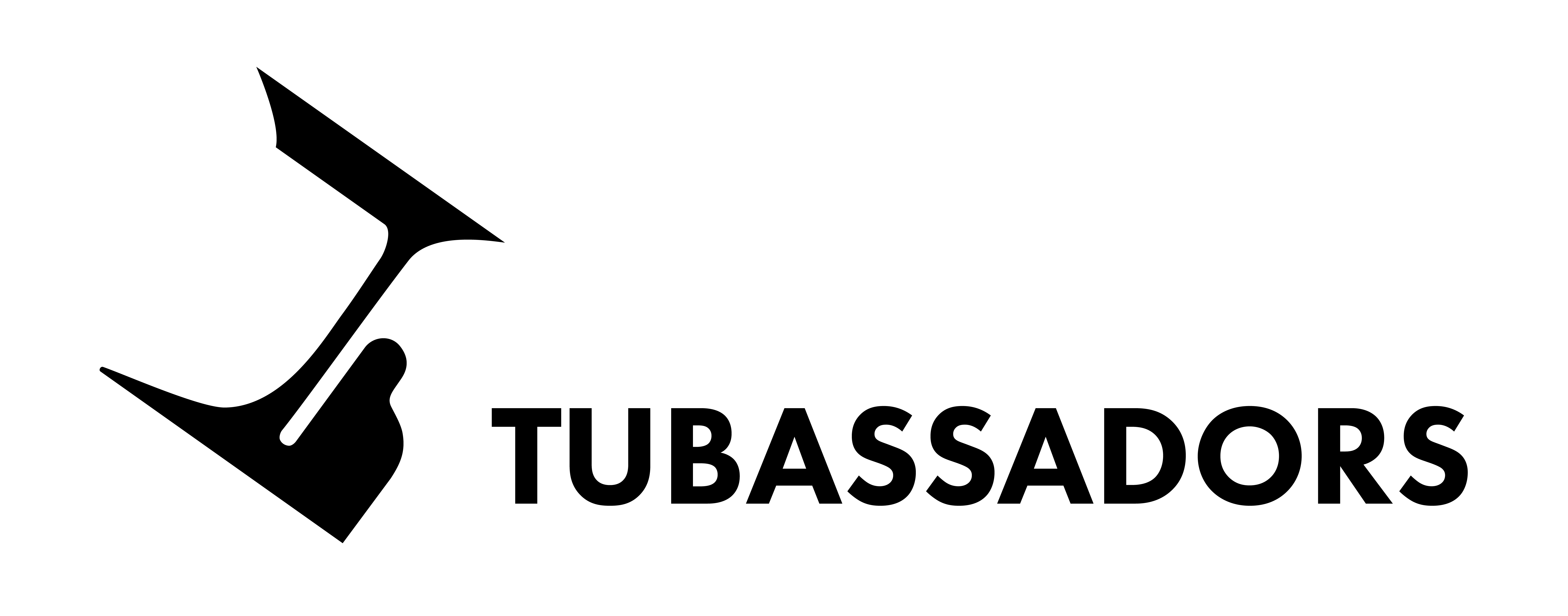「口の筋肉を鍛える」って本当に必要?
金管楽器を吹く人なら、一度くらいは先生や先輩から「もっとアンブシュアを鍛えなさい!」と言われた経験があるのではないでしょうか。
「唇の筋肉が弱いから音が出ない」とか、「鍛えれば音が安定する」と言われて、必死になって唇を鍛えようとした人も多いと思います。僕も実際やっていましたからね…。
実際、多くの奏者が「アンブシュア=筋肉の強さ」だと信じているので、唇を鍛えるために、長時間無理な練習をしたり、唇が痛くなるほど頑張ったりしています。
まず結論から書きますと
バズィングは唇の筋力アップ(筋トレ)を目的とした練習ではなく、正しい音程感覚と正しい息の流し方を習得するための練習です。
今回は筆者の主観がなるべく入らないように①科学的な視点からの分析と②世界的なプレイヤー達の意見の2つに分けてまとめていきます。
「アンブシュアの筋肉を強く鍛えるのがなぜ逆効果なのか」「限界まで練習して上達したよって人もいるけど、どういうこと?」!などなど、疑問に思うことがある方はぜひ最後まで読んでみてください
■科学的にはどうなの?
※あくまで自力で論文や文献を調べた中での話になります。この記事を鵜呑みにせず、ご自身で引用元などを参照ください。
1. 唇の筋肉(口輪筋)の特徴
まず、唇のまわりにある筋肉を「口輪筋(こうりんきん)」と言います。口輪筋は「表情筋」の一種で、主に食べること、話すこと、表情を作ることなど、細かく繊細な動きをするために存在しています。
この筋肉は話す、笑う、食べるなど繊細な動きを担う微細運動筋ですが、その筋線維構成は意外にも速筋(Type II 線維)が約71%と優勢であることが報告されています。※この内容は、口輪筋の筋線維について調べた医学論文(Stål et al., 1990)に基づいています。(リンク先で日本語訳すると概要が読めます)
噛み砕いて説明すると、口輪筋は「素早く細かい動きが得意」なタイプです。金管で言えば、音の出だしやタンギングの瞬間の調整など、短いオン・オフの切り替えに向いています。いっぽう頬の筋肉は「長くじわっと働き続けるのが得意」で、口の形を安定させる土台役。要するに、口まわりは「キビキビ動く担当(口輪筋)」と「支える担当(頬筋)」が協力して、演奏を助けている――このイメージが一番わかりやすいと思います。
また、北海道大学の研究チーム(大矢ら, 2009)は、「口の周りの筋肉=口輪筋」を強くしたり長く使えるようにするには、どれくらいの力で何回トレーニングすればよいかを検討しました。
その結果、筋力を高めたい場合は「1-RM(最大筋力)の80%を5秒かけ、5秒休む」を1回として5回、持久力を高めたい場合は「1-RMの50%で同様の5秒負荷・5秒休息」を1回として20回くり返す方法が有効と示されました(評価は14日後・28日後)。
これは条件次第では機能的なトレーニングが成立することを意味します。しかし、金管楽器の演奏にこれらの理論をそのまま当てはめられるかは別問題です。
ここで疑問になるのが、もし“筋肉さえ付けば演奏が安定する”のなら、研究のとおり高負荷の練習をすれば良いはずですが、実際にはそう単純ではない—という点です。
2.金管楽器の演奏は微細運動のコントロール
金管楽器の演奏は繊細な空気の流れと筋肉の協調運動(微細運動)によって成り立っており、これはスポーツ選手のように「筋力の出力を上げる」運動とは根本的に違います。
微細運動というのは、字の通り細かい筋肉を使って、とても繊細な動きをすることです。
例えばピアノを弾いたり、絵を細かく描いたり、裁縫をしたりするのも微細運動です。こうした運動は、出力の強いムキムキな筋肉があることよりも、脳や神経が細かく筋肉をコントロールすることが大切です。
アンブシュアを作るのに関係する筋肉には、口輪筋以外にも頬や顎の筋肉、舌の筋肉、そして息を調節するための胸やお腹の筋肉も関わっています。これらがバランス良く協調して動く必要があります。
ひとつの筋肉だけを鍛えるのではなく、「どの筋肉を、どのように動かせば、より良い音になるのか」ということを身体が学んでいくこと(これを「運動学習」と言います)が重要なんです。ただし、これは意識的にできることではないので、「良い音」を頭にイメージして練習を継続することで自動的に自分の体の使い方を頭に入れていくことが重要です。
こうした微細な動きをスポーツ的な「筋トレ」で鍛えようとするのは、「ヴァイオリンの弓の使い方を腕立て伏せで練習するようなもの」なのです。
楽器を鳴らすためにピアニストが指と腕をゴリゴリに鍛えてる人見たことないですよね。演奏家にはマッチョな人もいますが、演奏の中身には直接的には関係ありません。心身ともに健康的になることで良い演奏ができる効果は期待できるかもしれませんね。
筋力を鍛えるよりも、動きの感覚を全身で整えていくことが、効率的に演奏を上達させるコツです。
3.神経による保護機能(フェイルセーフ機構)
「唇の筋肉群をコントロールする神経には、損傷を予防するフェイルセーフ機構が備わっている。過度な使用で実際に唇の筋肉がダメージを受ける前に、神経は筋肉に信号を送るのをやめてしまう。そうなると、アンブシュアを維持するのは事実上不可能だ。」(F.マクウィリアム著「自分の音で奏でよう!」P55、ベルリン自由大学教授、生物学博士V・シュトルツ)
唇の筋肉をコントロールしているのは「顔面神経」という神経です。元ベルリンフィルのホルン奏者のF.McWilliamの本には、この神経には筋肉を守るための「安全装置」=フェイルセーフ機構があると紹介されています。正確には、顔面神経だけに特別な仕組みがあるのではなく、全身の神経と筋肉に共通して備わっている保護システムのことを指していますね。
たとえば、無理に唇に力をかけすぎたり、長時間練習しすぎたりすると、筋肉の中で疲労や痛みの信号が発生し、それが神経を通じて脳に伝わります。脳はその情報を受け取ると「これ以上使うと危ない」と判断し、筋肉を動かす信号を弱めたり止めたりします。その結果、いくら頑張っても唇が思うように動かなくなったり、音が出なくなったりします。
これは「神経が勝手にサボっている」のではなく、筋肉が壊れる前にブレーキをかける安全機能のようなものです。車のエンジンに付いているリミッターが、アクセルを思い切り踏んでもエンジンが壊れそうな回転数に達すると自動で出力が制限されるのと同じで、神経も筋肉が壊れないように自動でブレーキをかけています。
だからこそ、アンブシュアを無理やり「筋トレのように鍛える」ことはうまくいきません。必要なのは力比べではなく、繊細にコントロールできる神経系の学習=練習を通じた微調整なのです。
■ 世界的なプレイヤー達の意見は?
医学や生理学の視点から見ても、アンブシュアは「力で鍛える」ものではなく、「繊細にコントロールする」ものだということが分かってきました。ただ、この考え方は実はレジェンド的なプレイヤーが昔から口にしてきたことでもあります。
1.演奏は筋力の強化よりも神経系のコントロール(運動学習)によって洗練されていく
元シカゴ交響楽団首席チューバ奏者であり、世界中から金管楽器界のレジェンドと称されているアーノルド・ジェイコブス氏は、「音楽的イメージが身体の動きを導く」という考え方を徹底していました。
鏡を見ながら唇の形を整えるのではなく、「どんな音を出したいか」を思い描くことで、必要な動きは自然に整っていくという立場です。これは元ベルリンフィルホルン奏者のF.マクウィリアム氏も同じ意見を取っています。言い回しこそ違えど、世界中の著名なプレイヤーがほぼ同じことを書き残しています。
演奏で大きな「強さ|力」を使うと身体は機能しなくなる。筋肉は長時間にわたって、がっちりと固められると震えが起きてしまうのである。音楽家は解剖学について詳しく知る必要はない。だが、パワーではなく「最小限の動力」で音楽を創ることに熟達しなければならない。
by Arnold Jacobs (ブルース・ネルソン著「アーノルド・ジェイコブスはかく語りき」より)
エアが流れる気道、舌、あるいはアンブシュアに問題があっても無視する。音楽そのものの解釈に集中すれば見事に解決できる。間違っているのでは?と悩むのは、すでに自己分析に陥っているのだ。心配し、自己分析に陥り、数々の疑いを持つ、それらはすべて間違いだ!
by Arnold Jacobs (ブルース・ネルソン著「アーノルド・ジェイコブスはかく語りき」より)
『筋肉をしっかり固めた揺るぎのないアンブシュア』というと立派そうだが、実は硬い音色で柔軟性に欠ける演奏になってしまう。
By Fergus McWilliam
(F.マクウィリアム著「自分の音で奏でよう!」p.143より)
潜在意識は複雑な運動機能を作り出す力を持っている。意識的に邪魔をしなければ、音楽的な気づきが潜在意識を動かし、身体を自然に動かす。機能が音をつくるのではなく、音への意識が機能を生む。
by Sergio Carolino
(S.カロリーノ著 : Mind vs Metal, Paralysis by Analysis より)
2.口が痛くなるまでやったら上達した感がある現象について
「筋力じゃない」と言われても、毎日バズィングや練習を続けて、口が痛くなるほど頑張っていると、たしかに「上達した!」という実感があるかもしれません。練習をやった感、めちゃめちゃ出ますよね。
実際、ある程度の負荷をかけた練習によって、筋力や持久力が向上することも科学的には確認されています。ですから、「全く筋肉は関係ない」とまでは言い切れません。
でも、本当に大事なのは「筋肉がついたこと」ではなく、たくさん音を出す中で“良い音のイメージ”や“息の使い方”が身体や頭に繰り返し定着していくことです。
つまり、この場合の皆さんが感じる上達の正体は、筋力の成長というよりも、反復練習によって感覚と技術が洗練された結果なのです。
ただし、口が痛くなるまで無理をするのは逆効果です。唇が痛い状態というのは、すでに筋肉が限界を超えて、うまく振動できなくなっているサイン。そんな状態で無理に続けると、音が硬くなったり、アンブシュアのバランスが崩れてしまうことがあります。
演奏には唇だけでなく、呼吸筋や体幹など全身の筋肉のバランスも関わっています。練習はもちろん毎日できるのが理想ですが、「とにかくたくさんやればいい」という考え方だけではなく、回復や効率も考えた練習設計が大切です。
学生時代に1日8時間練習しまくったら上達した経験がある人は数多くいると思いますが、実際にはもっと効率良く練習することが可能です。
3.バズィングは筋トレではない
“The embouchure develops based on the music you play.”
「アンブシュアは、演奏する音楽に基づいて自然に発達していく。」
by Arnold Jacobs (Masterclass Memo 1993年7月30日より)
まず、医学・スポーツ科学における「筋トレ」とは、筋肉に負荷をかけて筋繊維を微細に破壊し、その修復過程でより太く・強くする(筋肥大)ことを目的とした運動です。つまり、筋力が落ちないように継続することや動きの質、コントロール(神経系)の向上は、この言葉の定義には含まれません。
金管楽器の練習方法として広く知られている「バズィング」。多くの人が「バズィング=唇を鍛える練習」と考えてしまいがちですが、実はこれもかなり危ない誤解です。
バズィングというのは、ただ唇を強くしたりするためにやる練習ではなく、「どんな音を出したいか=正確な音程感覚」「正しい息の吹き込み方」といった感覚を磨いていくための音楽的な練習方法です。
具体的に言うと、バズィングをするときに重要なのは、
①出そうとしている音程を頭の中で歌う
②その音程に適切な息の流し方
③バランス良く体をコントロールすること
筋力に任せて力まかせにやるのではなく、あくまで「音楽的なアイデアを持って取り組む」ことがポイントなんです。音楽的に取り組むことで神経や潜在意識が自動的に最適化されます。これは科学的に証明されている人体の仕組みの一つで、方法に着目するのではなく、結果に着目することが大事とされています。
その為、バズィングを「唇の筋トレ」と捉えてしまうと、「とにかくたくさん練習すればいい」「唇が痛くなったら効いている証拠だ」といった間違った考え方になり、逆に良い音を出すための感覚が育ちにくくなってしまいます。
“We need great knowledge of the art of sound and ignorance of physiology.”
「我々には音の芸術に対する深い理解が必要であり、生理学については無知であることが望ましい。」
by Arnold Jacobs (Masterclass 1993年7月26日)
■アンブシュアは「鍛える」よりも「バランスが大事」
科学的な根拠と巨匠達の意見を総合すると、「アンブシュアの筋肉を鍛える」という発想自体が金管楽器の上達を妨げていることが分かります。本当に大切なのは、力で唇を強化することではなく、息の流れや唇の動きをうまくコントロールできるようになること。
そのうえで、副産物として
低負荷で長時間の使用に耐えられる能力=「筋持久力」が向上しますし、唇の周りの筋力もついてきます。ただし、これを目的に練習することは大変な危険を伴います。
目的はあくまで、良い音をスムーズに豊かに鳴らすことで、それは無理に唇を痛めつけて得られるものではありません。
強い力で無理に吹き続けるのではなく、リラックスした無理のない奏法でコツコツを練習を続けることが大事です。
まとめ
・口輪筋は理論上はトレーニング可能だが、筋トレではなくコントロール強化が本質
・「強くする」より「上手に使う」ことを目指すべき
・バズィングは筋力強化ではなく、音楽的・感覚的な訓練である
・無理のない反復練習で微細な動きを学習することが、上達の近道
まとめるとこんな感じですね。
無理のない自然な奏法の獲得が大事!
といっても実際には多くの人がこの壁にぶつかっています。痛めつけるような練習ではなく、どうすれば息と動きがバランスよく整っていくのか。頭で分かっても、ひとりで練習していると迷ってしまうことも多いと思います。
そうした悩みに応えるために、チューバサダーズはBASSAZAP PRO(バサザップ・プロ)というレッスンサービスを展開しています。演奏動画へのフィードバックや課題設定を通して、「無理のない奏法」が自然に身につくことを目指しています。
今ならチューバサダーズの公式LINEに登録するだけで、ワンポイントレッスン動画10本を無料でプレゼントしています。
気になる方は、気軽にチェックしてみてください!