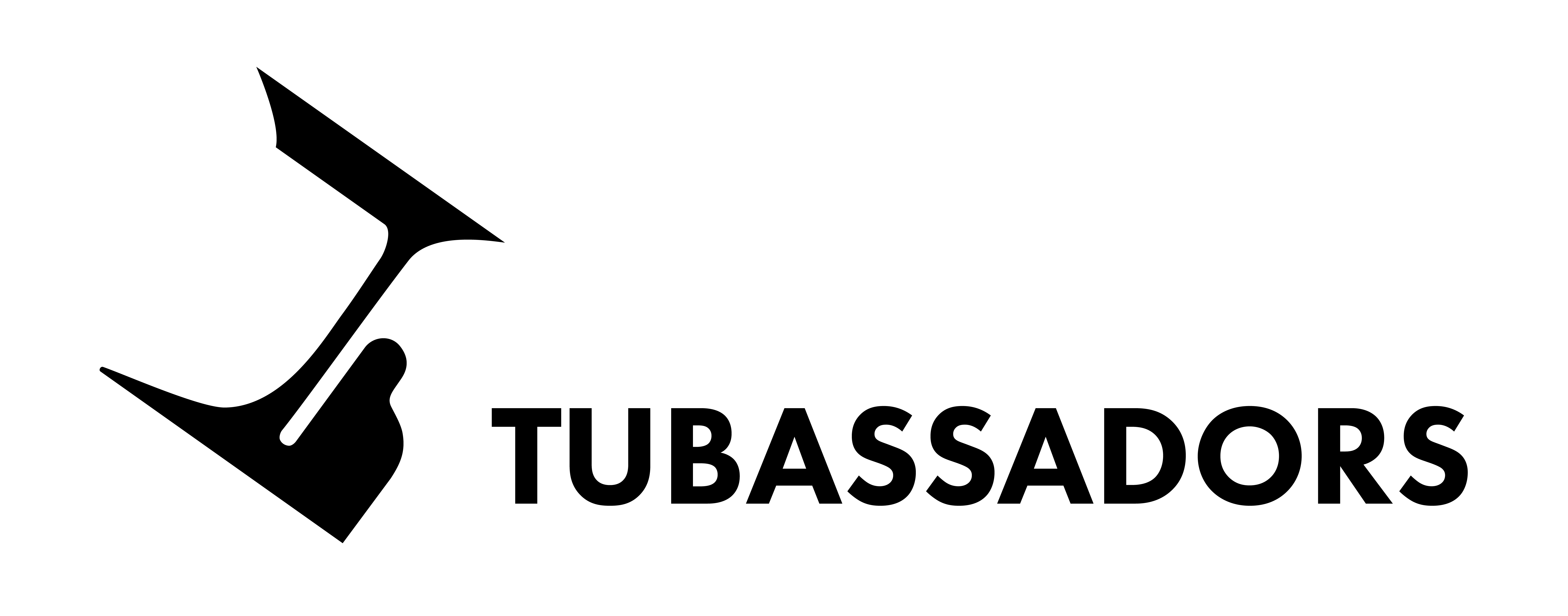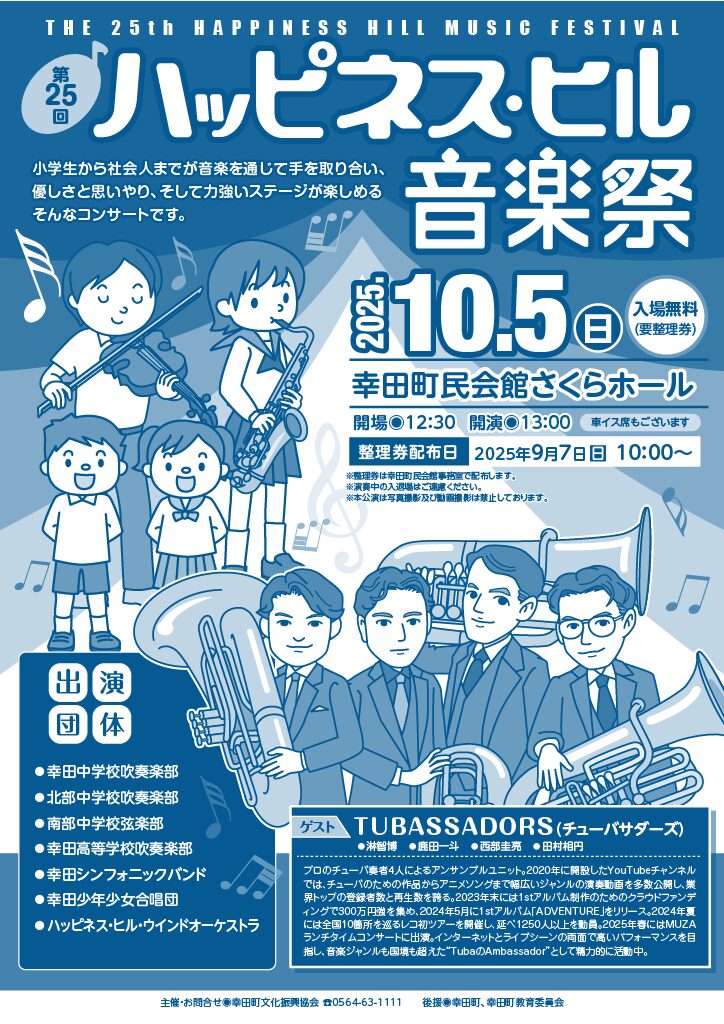はじめに
楽器に使うグリスやオイルにこだわると音が良くなる!みたいな話聞いたことありませんか?
「え、音変わるの?!」と、そんな事考えたことなかった人もいると思いますが、実際たくさん種類があってどれを選べばいいか悩みますね。
今日は、意外と誤解の多い 「オイル・グリス」 の話をしたいと思います。
結論から言えば――
プロが使うのは高級なものや特殊なものではなく、ヤマハやヘットマン、JMルブリカントといった高品質で定番の楽器用オイル・グリスです。
微妙に相性みたいなものもあるので、詳しく解説していきます。チューバへの使用を前提とした話になりますので、他の楽器の方は参考までにどうぞ。
1. グリス選びのポイント
まず、グリスについてですが、基本的にはまずは各社から販売されている「レギュラーグリス」を使うと良いでしょう。
グリスを選ぶ時に大切なのはスタンダードなものを選ぶことです。
スタンダードな粘度のものを使うことで、技術的に自分に何が足りないのかを判断しやすくなり、様々なスタイルの楽曲へ対応することもできます。
チューバサダーズが度々動画でも話す、「自分にとってのニュートラルな状態を作っておく」という考え方に近いところがありますね。
スタンダードなものでも各社わずかに重さや音が違ってきます。
自分の好みに合うものを見つけると良いでしょう。後半に代表的なメーカーの詳細をまとめています。
いざ、選ぶとなった時に、気をつけることはなるべく大きな部屋で吹くことです。
小さい部屋では「抵抗感が気持ちよく感じる」ことが多いのですが、広い部屋では抵抗が強すぎると感じることがあります。広い部屋で試すことはグリスに限らず、オイルやマウスピース、その他カスタムパーツなどを選ぶ時も大切なことなので、覚えておくと役に立つと思います。

また、抜差管が演奏中に緩んで落ちてしまうほどスカスカな場合の解決方法は「芯金」という金属棒を使い、ハンマリングによって抜差管をほんの僅かに太くする「嵌合調整」を行う必要があります。
重いグリスで一時的には改善しますが、管の隙間は変わらないので、そこにオイルが流れ込むことでグリスが溶けてしまいます。そうなるとまた緩くなってしまうので、根本的な改善にはなりません。グリスを塗り直す頻度が増えれば管の中も汚れやすくなります。
もちろん、ヘビータイプのグリスの音が好きだ!という方は自分の感覚を信じてそれをセレクトすると良いでしょう。
あくまで、楽器の機能面として演奏中に落ちてきてしまうような抜差管に対しては、本来修理が必要となります。
2. オイルの粘度について
基本的には多くの人が「レギュラー」タイプで十分です。
ヴィンテージ楽器に関しても、レギュラーで動きが悪くならないのであれば、無理に粘度の高いものを使う必要はないです。むしろ、ピストンやロータリーの動きの悪さはオイルが原因ではなく、基本的な調整不良なことがほとんどです。
また、音色に関しても、「粘度が軽い=明るい音」「粘度が重い=暗い音」といった特徴はあります。ポップスではライトオイルを使い、クラシックではレギュラーを使う、といった使い分けをする人もいます。
季節や温度に応じた粘度調整も重要ですね。
- 真夏(35℃前後):オイルは揮発しやすく、軽く感じやすい
- 真冬(3℃前後):オイルが固く感じ、動きが鈍くなる
夏場に軽い同じオイルを使い続けるなら、指す頻度を増やす必要があります。逆に冬場に重いオイルを使うと動きが鈍く感じるかもしれません。お住まいの地域に合わせて調節するとよいでしょう。

3. おすすめのメーカー
※基本はユーフォニアムやチューバを前提とした話になります。楽器が小さくなれば石油蒸留物系オイルの選択肢もありますし、注油量の条件も変わるので、参考までにお願いします。
ヤマハ(YAMAHA, Japan)
世界最大級の総合楽器メーカー。ピアノや電子楽器から管楽器まで幅広く手がけ、世界120以上の国と地域に流通網を持っています。
オイルやグリスも自社楽器に合わせて研究・開発されており、化学的に安定し、金属やラッカーを守る設計。実際にチューバサダーズのメンバーも、ヤマハのグリスを使用している人が多いです。(オイルは様々)
品質は非常に高く、初心者から上級者までおすすめです。音色への余計な色付けが無く、全オイル・グリスメーカーの中で最もニュートラルです。良くも悪くもですが、楽器が持っている音色や鳴りを邪魔しないのが特徴です。
特にSG4というレギュラーグリスはとてもいいですね。一つの基準として、これを試して抜差管が緩い場合は、嵌合調整をしても良いかもしれません。
防腐剤も入っており、管の内側をサビから守ってくれます。
2. ヘットマン(Hetman, USA)
1980年代に誕生した、楽器用オイルに特化したブランド。最大の特徴は、粘度を細かく分けた豊富なラインナップ(No.1〜No.14など)で、楽器や環境に合わせて選べます。
北米やヨーロッパを中心に世界的に流通しており、特にプロ奏者からの信頼が厚いブランドです。一時期、流通量が著しく少なくなってしまいましたが、最近は手に入りやすくなりました。こちらも古くからある高品質なオイルです。
ヤマハと比べるとやや音に響きが乗ります。倍音なのか、吹奏感なのか、とにかく独特のサウンドを持っていて、ヘットマンファンの人は世界中にいます。
3. ラ・トロンバ(La Tromba, Switzerland)
1970年代にスイスで設立された老舗ブランドです。バルブオイル、スライドオイル、コルクグリスなど幅広い製品を展開しており、ヨーロッパでは学生からプロ奏者まで広く使われています。吹奏楽部や音楽教育の現場でもよく見かけられ、“ヨーロッパの定番ブランド”として確かな地位を築いています。
2013年に創業者の I. Hemmeler 氏が逝去した後は、La Tromba AG と Chemische Fabrik Schachen(CFS) の2社体制となり、それぞれが製品を展開しています。
日本でも「T2」という青いキャップのオイルは人気が高く、使いやすさや反応の良さ、響きの豊かさを理由にファンが多いです。特にピストンチューバで使う方が多い印象があり、やはり“定番のサウンド”という安心感がありますね。
一方で、キャップが壊れやすいという声もあります。また、ヤマハやウルトラピュアのような合成油ではなく鉱油(ミネラルオイル)ベースなので、独特のにおいがします。
グリスの方は木管楽器奏者からの評価も高く、ホルン吹きの愛用者も多いです。チューバだとパッケージが小さめなので割とすぐに使い切ってしまうのと、楽器によっては響きが豊かすぎて“モヤッとした感じ”になることもあります。


4. ウルトラピュア(Ultra-Pure, USA)
1990年にアメリカで誕生したメーカーです。創業以来、楽器奏者にとって理想的なオイルを追求し、「速く、軽く、滑らかでシルキー」という吹奏感を実現することを目指して製品づくりを続けてきました。
ウルトラピュアの大きな特長は、合成油ベースで無臭・非毒性という点です。香りが気にならず、オイルの残留や着色も少ないため、清潔に安心して使うことができます。また、非可燃性で航空便にも対応可能とされており、安全性への配慮も徹底されています。
製品ラインアップは幅広く、標準タイプの「プロフェッショナル」、軽快さを求める方向けの「ウルトラライト」、そして少し重めの設計で摩耗したピストンや大型楽器におすすめの「Black Label Classic」などがあります。
チューバ奏者の方には、このブラックラベルがおすすめで、ほんのり音に薄い膜をかけて守ってくれるような響きが得られます。ヤマハのオイルが「素直すぎる」と感じたときに、ウルトラピュアを試してみてください。
さらに近年では、大手楽器メーカー Eastman Music Company のグループに加わり、グローバルでの供給体制も強化されました。これにより、これまで以上に安定して製品が手に入るようになっています。
オイルだけでなく、グリスも3種類用意されています。
- ヘビータイプは水飴のようにとても粘度が高く、抜差管が緩すぎるときの緊急対策としては効果的ですが、通常使用ではお勧めしません。
- ライトタイプはヨークモデルのように演奏中に頻繁に動かす抜差管や、トランペットでの使用に向いています。チューバで普段使いするには軽すぎる印象です。
- レギュラータイプは適度な粘度があり、独特の「響きの丸さ」が特徴です。自然な吹奏感でありながら、音を守ってくれる安心感があるため、好んで使う方も多いです。
どのラインナップも、少しだけ響きをまとってツヤが出るので、これがメーカーが言う「シルキーな音」の傾向なのかもしれません。
5. JMルブリカント(JM Lubricant, Germany)
ドイツを拠点とする「J. Meinlschmidt GmbH」は、1866年からロータリーバルブ製造に携わってきた歴史ある企業です。ロータリー楽器(ホルンやチューバ)向けの設計に強みがあり、金管奏者から高い評価を得ています。
近年のB&Sやマイネルウェストンを製造している、マルクノイキルヘンの工場でも使用されており、ドイツ製チューバへ使用するオイルとして、非常に適しています。ヤマハのロータリーオイルは1種類しか無く、マイネルウェストンやB&Sの楽器ではやや反応が重たいような印象もありますので、こちらがおすすめ。
特にヨーロッパでの支持が厚く、管楽器愛好家の間で愛用されています。ピストン用ももちろん良いですが、やはり“ロータリー楽器に強いブランド” と言えます。
4.道具に頼りすぎないこと
オイルやグリスは、確かに「快適に楽器を使うための助け」として重要な役割を果たします。粘度や種類の違いで吹奏感が変わるのも事実ですし、状況に応じて選ぶこと自体は演奏の工夫の一つと言えるでしょう。
ただし、それを「音を作るための中心的な手段」と考えてしまうのは危険です。
例えば「このグリスに変えたらドッペル(発音の濁り)直った!」としても、それは「長期的には自分で音をコントロールする技術の向上を妨げている」かもしれません。
この「道具に頼りすぎない」という考え方は、多くの名手達の言葉によって裏付けられています。
例を挙げると…
- ファーガス・マクウィリアム(ドイツ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 元ホルン奏者)
「道具やメソッドに依存しすぎると、本質を見失う」
→ 道具を工夫すること自体は否定されないが、依存しすぎるほど奏者の本質から離れてしまう。 - セルジオ・キャロリーノ(ポルトガル ポルト国立交響楽団 首席チューバ奏者)
「楽器そのものではなく、音楽への意識と心の在り方が演奏を決める」
→ オイルやグリスが補助的に役立つことはあっても、演奏の核心はあくまで奏者自身の内面にある。
まとめ
いかがだったでしょうか!グリスやオイルは身近なものだからこそ、プロはどういうものを使っているのか気になりますよね。選び方としても、基本は定番のもので良いでしょう。ドイツ製だから必ずしもドイツ製のオイルを使ったほうがいいわけでもないですし、シンプルに安くて高品質なヤマハを使うのがファーストチョイスかなと思います。
そのうえで、もう少し抵抗や響きがほしければ、ヘットマンやラ・トロンバを試してみてください。ポイントは狭い部屋で一人で判断しないことですね。良くなった気がするのはグリスで高音域の倍音が減って演奏の粗が目立ちにくくなっているだけかもしれません。逆にライトオイルで、パキパキ吹きやすいと思っていたら出ている音はかなりノイジーだったりと…。先入観で、値段の高いものを良いと感じてしまったり、案外難しいんです。
忘れてはならないのが、どんなオイルでもまずは定期的な洗浄と調整、オイル乾いてしまわないようにこまめに指す。これが何より大切です。
何かの参考になれば幸いです